2025年も落ちた。33点合格点のところ、32点。あと1点…非常に悔やまれる結果となった。
もう受けるの止めようかと思うが、来年も受けてしまうんだろうな。つけた知識(どれくらい覚えてるかわからないけど)がもったいなすぎる。
農地法
3条は「権利移動」農業委員会
4条は「転用」都道府県知事
5条は「転用目的の権利移動」都道府県知事
4.5条の市街化区域特例→農業委員会への届け出のみで良い。市街化したいから。
新築〜6か月で売れないと不動産所得税課される。
50-240㎡以下1200万円控除。
去年も受けているのに全然通用しない。全然覚えていない。そもそも勉強していない。3日前に音読して、ボイスレコーダーに吹き込んだのを忘れている。
なんて馬鹿なんだと絶望する。同じ問題が解けない。まるで違う問題を見ているように、意地悪な選択肢が不安にさせる。それでも解いて解いて解きまくるしか残された道はない。
(1)
都市計画区域は、原則として、都道府県が指定するが、都市計画区域が2以上の都府県にまたがるときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得て指定する。
×
都市計画区域は、原則として、都道府県が指定する(都計法5条1項)。ただし、2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する(同条4項)。
(8)
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う規模が1,500㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
〇
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものをしようとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない(都計法29条1項2号)。しかし、市街化区域内において行う開発行為には、この農林漁業用建築物を建築するための開発行為の例外は適用されない。したがって、本問の場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(12)
開発許可を受けた者は、開発区域の位置、区域及び規模を変更しようとする場合においては、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
×
開発許可を受けた者は、開発区域の位置、区域及び規模や開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(予定建築物等)の用途などを変更しようとする場合には、原則として、都道府県知事の「許可」を受けなければならない(都計法35条の2第1項本文)。
(14)
2階建て又は延べ面積が200㎡を超える建築物の新築をしようとする者は、工事に着手する前に、建築計画が建築基準法令に適合しているかどうかの確認を受け、検査済証の交付を受けなければ、工事に着手することができない。
〇
2階建て又は延べ面積が200㎡を超える建築物の新築をしようとする者は、工事に着手する前に、建築計画が建築基準法令に適合しているかどうかの確認を受け、検査済証の交付を受けなければ、工事に着手することができない(建基法6条1項)。
https://e-takken.tv/r02-17/
(20)
建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物には、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限は適用されない。
×
建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物の建ぺい率は、都市計画で定められた建蔽率の限度に10の1を加えた数値が建蔽率の限度となる(建基法53条3項1号イ)。
(21)
第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち、特定行政庁により定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
×
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する「都市計画」において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(建基法55条1項)。
(22)
市街化調整区域内の建築物についても、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)が適用される。
×
道路斜線制限は、すべての用途地域で適用される(建基法56条1項、同法別表第三)。したがって、原則として用途地域を定めない市街化調整区域内の建築物に、道路斜線制限が適用されるとはいえない。
(24)
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
×
宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事以外の宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、「工事主」は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない(盛土規制法12条1項)。
(25)
開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可をいう。)を受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事については、宅地造成等に関する工事の許可を受ける必要はない。
×
宅地造成等に関する工事の許可を受ける必要がないのは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事である(盛土規制法12条1項)。旧宅造法に規定されていた本問のような例外は、盛土規制法には設けられていない。
(33)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
×
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、一定の場合を除き、当事者が「農業委員会」の許可を受けなければならない(農地法3条1項)。
(35)
市街化区域内では2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域内では5,000㎡以上、準都市計画区域を含む都市計画区域外では10,000㎡以上の土地について、土地売買等の契約を締結したときは、都道府県知事に、国土利用計画法第23条の事後届出をしなければならない。
〇
届出対象面積にあたる土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、都道府県知事に国土法23条の届出をしなければならない(同法23条2項1号イ~ハ)。
【届出対象面積】
①市街化区域 2,000㎡以上
②市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
③準都市計画区域を含む都市計画区域外 10,000㎡(1ha)以上
(49)
標準地が、都市計画区域外から選定されることはない。
×
標準地は、公示区域内の土地から選定されるが、公示区域とは、国土法の規定により指定された規制区域を除く、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域をいう(地価公示法2条1項)。したがって、土地取引が相当程度見込まれる区域であれば、都市計画区域外から選定されることもあり得る。
特定盛土宅地造成
(5)
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え:×
宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事以外の宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、「工事主」は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない(盛土規制法12条1項)。
(7)
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について、当該宅地造成等工事規制区域の指定後に、開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可をいう。)を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、宅地造成等に関する工事の許可を受けたものとみなされる。
答え:○
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について、当該宅地造成等工事規制区域の指定後に、都市計画法29条1項又は2項の開発許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、宅地造成等に関する工事の許可を受けたものとみなされる(盛土規制法15条2項)。

(10)
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が300㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。
答え:×
宅地以外の土地を宅地にするために行う「切土」であって、当該切土をした土地の部分に高さが「2メートルを超える」崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成にあたる(盛土規制法施行令3条2号)。したがって、本問事例の場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであるから、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
切土の方が安全だから2m以内、盛った方が崩れやすい。
(14)
宅地造成等工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
答え:×
宅地造成等工事の許可を受けた者は、一定の場合を除き、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の「許可」を受けなければならない(盛土規制法16条1項)。
(19)
公共施設用地を除く宅地造成等工事規制区域内の土地において、高さが2mを超える擁壁等の全部を除却する工事を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の許可若しくは変更の許可を受け、又は変更の届出をした者を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨について都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え:×
公共施設用地を除く宅地造成等工事規制区域内の土地において、以下の工事を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の許可若しくは変更の許可を受け、又は変更の届出をした者を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に「届け出」なければならない(盛土規制法21条3項、同法施行令26条1項)。
①擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるものの全部又は一部の除却の工事
②地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事
(20)
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用した場合は、一定の者を除き、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、農地を転用した場合には、このような届出をする必要はない。
答え:×
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を「宅地」又は「農地等」に転用した者は、宅地造成等に関する工事の許可若しくは変更の許可を受け、又は変更の届出をした者を除き、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(盛土規制法21条4項)。
土地区画整理法
(4)
土地区画整理組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望する独立行政法人都市再生機構は、当該組合の組合員となれる場合がある。
答え:○
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であって、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる(区画法25条の2)。
(5)
土地区画整理組合の総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
答え:×
組合員の「半数」以上が出席しなければ開くことができない(区画法34条1項)。
土地区画整理組合の総会の会議の議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる(区画法34条1項)。
(7)
土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるための賦課金を、参加組合員に対して賦課徴収することができる。
答え:×
賦課金として参加組合員「以外」の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる(区画法40条1項)。
(9)
土地区画整理事業が、土地区画整理組合などが施行者となるいわゆる私的施行であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならないが、市町村や機構等が施行者であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受ける必要はない。
答え:×
土地区画整理事業の施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない(区画法86条1項後段)。
(10)
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
答え:○
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない(区画法89条1項:換地照応の原則)。
要するに、換地は、可能な限り、従前の宅地と釣り合いが取れたものになるように定めなければならないという原則である。
(11)
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないが、当該土地区画整理事業の施行に同意していない施行地区内の土地所有者は、都道府県知事等の許可を受けることなく、土地の形質の変更を行うことができる。
答え:×
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業では、設立の認可やその基準等の公告、又は事業計画の変更についての認可の公告があった日から、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある以下の行為を行おうとする者は、都道府県知事などの許可を受けなければならない(区画法76条1項、同法施行令70条)。
①土地の形質の変更
②建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
③その重量が5tを超える移動の容易でない物件の設置若しくは堆積
土地区画整理事業の施行に同意していない施行地区内の土地所有者であっても、上記のような行為をするときは、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
(15)
仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を第三者に譲渡することはできない。
答え:×
仮換地の指定により、従前の宅地の所有者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、その従前の宅地を使用又は収益することができなくなるが(区画法99条1項)、従前の宅地の処分権はある。つまり、従前の宅地の使用収益権はないが、処分権は残されている状態になる。したがって、従前の宅地を第三者に譲渡することもできる。
(16)
仮換地の指定の効力は、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときでも、仮換地の指定に際して通知した仮換地の指定の効力発生の日に生じる。
答え:×
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するとき、その他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を「仮換地の指定の効力発生の日」と「別に」定めることができる(区画法99条2項前段)。必ずしも「仮換地の指定の効力発生の日」に限らない。
(20)
仮換地の指定の効果は、換地処分の公告があった日の翌日に消滅する。
答え:×
仮換地の指定の効果は、換地処分の公告があった日が終了した時に消滅する(区画法99条1項参照)。換地処分の公告があった日の翌日に消滅するのではない。
(21)
換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日が終了した時に確定する。
答え:×
換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する(区画法104条8項)。換地処分の公告があった日が終了した時に確定するのではない。
(22)
土地区画整理組合が施行者である土地区画整理事業では、換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、土地区画整理組合が取得する。
答え:○
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する(区画法104条11項)。したがって、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業では、土地区画整理組合が換地処分の公告があった日の翌日に保留地を取得することになる。
農地法
(1)
開墾した原野を、現に農地として耕作している土地は、土地の登記簿上の地目が原野であっても、農地法の適用を受ける農地である。
答え:○
農地法上の農地に当たるか否かは、その土地の客観的な現況により判断される。したがって、登記簿上の地目が原野であっても、現に農地として耕作されているのであれば、農地法上の農地に当たる。
(4)
農家が、農業経営に必要な資金を金融機関から借り入れるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条第1項の許可を受けなければならない。
答え:×
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくは「その他の使用及び収益を目的とする権利」を設定し、若しくは移転する場合には、一定の場合を除き、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない(農地法3条1項)。抵当権を設定しても使用収益権は設定者のもとに留まるから、抵当権の設定は「その他の使用及び収益を目的とする権利」の設定・移転には当たらない。したがって、農地法3条の許可を受ける必要はない。
市街化区域内の農地を農地以外に転用、又は転用する目的で権利移動する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法4条又は5条の許可を受けなくてもよいとする例外がある(同法4条1項7号、5条1項6号)。しかし、農地法3条の許可については、このような例外は設けられておらず、原則どおり農地法3条1項の許可を受けなければならない。
農地法3条1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。したがって、本問の売買契約は無効であり(同条6項)、農地の所有権は買主に移転しない。
(7)
相続により農地を取得するときは、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遺産の分割や相続人への特定遺贈により農地を取得するときは、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
答え:×
農地又は採草放牧地について、所有権などの権利を、相続、遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈などにより取得したときは、農地法3条1項の許可は要しないが、遅滞なく、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない(農地法3条の3、同法施行規則15条5号)。
(8)
耕作目的で山林を農地に転用しようとする場合、都道府県知事等の許可(農地法第4条第1項の許可をいう。)を受けなくてもよい。
答え:○
農地法にいう「転用」とは、農地を農地以外のものにすることである(同法4条1項)。したがって、山林や原野などの農地以外の土地を農地に転用する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。農地の保護が農地法の目的であるから、農地以外の土地を農地に変更することは、農地法の規制対象にはならない。
(9)
市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可(農地法第5条第1項の許可をいう。)を受ける必要はない。
答え:×
「市街化区域」内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要はないが(農地法5条1項6号)、市街化調整区域内の農地には、この例外は適用されない。したがって、原則どおり、都道府県知事等の許可を受ける必要がある(同項)。
(10)
農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあれば、その後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
答え:×
農地又は採草放牧地の「賃貸借」は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる(農地法16条)。ここに「使用貸借」は含まれない。
国土利用計画法
(1)
個人Aが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地に、個人Bが、所有権を移転する契約を締結したときは、Bは一定の場合を除き、事後届出(国土利用計画法第23条の届出をいう。)を行わなければならないが、地上権の設定を受ける契約や賃借権の設定を受ける契約を締結したときは、事後届出をする必要はない。
答え:×
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)は、都道府県知事に届け出なければならない。ここにいう土地売買等の契約とは、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利をいい、土地に関する地上権及び賃借権がこれにあたる(国土法23条1項、14条1項、同法施行令5条)。したがって、Bは一定の場合を除き、事後届出を行う必要がある。
贈与は事後届出不要。「対価を得て」行われる移転又は設定により土地に関する権利を取得した場合に、国土法23条の事後届出をしなければならない。
(7)
Aが、国土利用計画法の注視区域、監視区域のいずれにも指定されていない市街化区域内の一団の土地を分割して、Bに1,200㎡、Cに500㎡、Dに600㎡を順次売り渡す場合、B、C及びDは、国土利用計画法第23条第1項の届出をしなければならない。
答え:×
取引される個々の面積は届出対象面積に満たなくても、権利を譲渡する土地の面積の合計が届出対象面積以上となる場合(いわゆる「売り」の一団)には、事後届出をする必要はない。売りの一団について届出を要するのは、規制区域、監視区域における事前届出の場合だけである。
(8)
市街化区域内のA市が所有する3,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Bが買い受けた場合、Bは事後届出を行わなければならない。
答え:×
当事者の一方又は双方が国等である場合、届出対象面積以上の土地の売買等の契約であっても、事後届出をする必要はない(国土法23条2項3号)。したがって、本問のBは、事後届出をする必要はない。
税について
(3)
家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の最初の使用者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税が課される。
答え:×
家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税が課される(地方税法73条の2第2項本文)。
都道府県は、相続、包括遺贈及び「被相続人から相続人に対してなされた」遺贈による不動産の取得に対して、不動産取得税を課すことはできない(地方税法73条の7第1号)。
(7)
令和4年に新築された床面積が150㎡の中古住宅を、個人が自己の居住のために取得した場合、その中古住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、その住宅の価格から1,200万円が控除される。
答え:○
個人が、床面積50㎡以上240㎡以下の既存住宅を、自己の居住の用に供するために取得した場合における不動産取得税の課税標準の算定については、その住宅の築年数に応じて最高1,200万円が控除される。平成9年4月1日以降に新築された既存住宅であれば、不動産取得税の課税標準から1,200万円が控除される(地方税法73条の14第3項、同法施行令37条の18第1項、3項)。
(8)
土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が20万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。
答え:×
不動産取得税の課税標準となるべき額が、以下の額に「満たない」場合においては、不動産取得税を課すことはできない(地方税法73条の15の2第1項)。
①土地の取得 10万円
②家屋の取得のうち建築に係るもの(新築・増築・改築) 23万円
③家屋の取得のうち、建築以外によるもの(売買・贈与・交換など) 12万円
不動産取得税の標準税率は、100分の4であるが(地方税法73条の15)、この税率は、あくまでも地方団体が課税する場合に「通常よるべき税率」であって、地方団体が財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない(同法1条1項5号)。したがって、都道府県は、財政上その他の必要があると認める場合には、100分の4を超える税率で不動産取得税を課すこともできる。
令和9年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合には、不動産取得税の標準税率を100分の3とする税率の特例が適用されるが(地方税法附則11条の2第1項)、住宅用「以外」の建物の取得に対しては、「100分の4」の本則税率が適用される(同法73条の15)。
固定資産税は、固定資産の所有者に課されるのが原則であるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者に課される(地方税法343条1項)。
(14)
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に係る固定資産税は、区分所有に係る建物の各区分所有者が連帯して納付する義務を負う。
答え:×
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に係る固定資産税は、原則として、持分の割合により「按分した額」を、区分所有に係る建物の各区分所有者が納付する義務を負う(地方税法352条の2第1項)。連帯して納付する義務を負うのではない。
もっぱら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地(住宅用地)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされる(地方税法349条の3の2第1項:住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)。ただし、住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とされる(同条2項)。一律に3分の1の額とされるわけではない。
固定資産税の標準税率は、100分の1.4である(地方税法350条1項)。ただし、市町村は、一定の場合には、当該市町村の議会において納税義務者の意見を聴いて、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して100分の1.7を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定することができる(同条2項)。
固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定められるのが原則であるが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることもできる(地方税法362条1項)。
(18)
不動産売買契約書には印紙税が課税されるが、土地賃貸借契約書には印紙税は課税されない。
答え:×
印紙税が課税される文書(課税文書)のうち、覚えておくべきものは次のとおりである(印紙税法別表第一1号の1、1号の2、2号、印紙税法基本通達13条)。
①不動産の譲渡に関する契約書
売買契約書、交換契約書、贈与契約書など
②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
③請負に関する契約書
工事請負契約書、請負金額変更契約書など
よって、不動産売買契約書だけではなく、土地賃貸借契約書にも印紙税が課税される。
(19)
印紙税法に規定する契約書とは、契約当事者の間において、予約を含む契約の成立、更改又は内容の変更並びに消滅、若しくは補充の事実を証明する目的で作成される文書をいう。
答え:×
印紙税法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(契約の成立等)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の「消滅」の事実を証明する目的で作成される文書は「含まない」(印紙税法基本通達12条)。
記載された受取金額が5万円未満の受取書には、印紙税は課税されない(印紙税法別表第一17項)。
(23)
Aの所有する価額4,000万円の土地をBに贈与する旨の贈与契約書は、印紙税の課税標準となる記載金額はないものとして取り扱われる。
答え:○
贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱われる(印紙税法基本通達23条(1)ホ)。
(25)
個人又は法人が、令和8年3月31日までの間に土地の売買による所有権の移転の登記を受ける場合の登録免許税の税率は1,000分の20である。
答え:×
土地の売買による所有権の移転登記の本則税率は1,000分の20であるが、個人又は法人が、令和8年3月31日までの間に売買による所有権の移転の登記を受ける場合の登録免許税の税率は1,000分の15に軽減される(租税特別措置法72条1項)。
(26)
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率を1,000分の3に軽減する措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用を受けることができる。
答え:×
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率を1,000分の3に軽減する措置は、住宅用家屋のみに適用され、敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記には適用されない(租税特別措置法73条、同法施行令42条1項)。土地の売買による所有権の移転登記等については、別に税率の軽減措置が設けられている(同法施行令72条1項)。
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置の適用対象となる家屋は、個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上のものでなければならない(租税特別措置法73条、同法施行令42条1項1号、41条1号)。
(28)
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率を1,000分の3に軽減する措置は、一定の耐震基準を満たしていることが証明された家屋に限り適用を受けることができる。
答え:×
建基法施行令の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するもの、又は「昭和57年1月1日以後に建築されたもの」であれば、
住宅用の家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率を1,000分の3に軽減する措置の適用を受けることができる(租税特別措置法73条、同法施行令42条1項2号)。
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置の適用を受けるためには、適用対象となる住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けなければならない(租税特別措置法73条)。
(30)
過去に住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けたことがある者であっても、再度この措置の適用を受けることができる。
答え:○
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置の適用回数に制限は設けられていない(租税特別措置法73条)。したがって、過去に税率の軽減措置の適用を受けたことがある者であっても、再度この軽減措置の適用を受けることができる。
建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする借地権又は地役権の設定である場合、対価として支払を受ける金額が土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、資産の譲渡とみなされ、譲渡所得として課税される(所得税法33条1項、同税法施行令79条1項1号)。
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費には、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額(購入代金)、建築代金、購入手数料のほか、設備費及び改良費の額も含まれる(所得税法38条1項)。
(33)
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は、15%の税率で所得税が課税される。
答え:○
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得に、5年以下の場合は短期譲渡所得になり(所得税法33条3項)、長期譲渡所得には100分の15(15%)、短期譲渡所得には100分の30(30%)の税率で、所得税が課税される(租税特別措置法32条1項、3項)。
個人が有する居住用財産を譲渡したことによって、3,000万円以上の譲渡利益が生じた場合、一定の要件を満たせば、その所有期間の長短にかかわらず、課税譲渡所得金額を計算する上で最高3,000万円が控除される(租税特別措置法35条1項:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。なお、譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、特別控除額は、譲渡所得の金額が限度となる。
配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対する譲渡の場合、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法35条2項1号かっこ書)。ここにいう特別の関係がある者には、当該個人の直系血族が含まれる(同法施行令20条の3第1項1号、23条2項)。子は直系血族であるから、子に譲渡した場合には、生計を同一にしているか否かにかかわらず適用を受けることはできない。
(37)
個人が令和7年中に令和7年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の適用を受けるときであっても、重ねて居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができる。
答え:○
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例と重複して適用を受けることができる特例の組み合わせは、次のとおりである。
①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率 ←→ 収用等が行われた場合の5,000万円の特別控除
②居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率 ←→ 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除
したがって、本問の場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の適用を受けるときであっても、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の適用を受けることができる。
(38)
親からの贈与により財産を取得した子が、贈与年の1月1日において18歳以上であれば、贈与者である親の年齢にかかわらず、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の適用を選択することができる。
答え:×
贈与により財産を取得した者が贈与年1月1日において18歳以上の贈与者の直系卑属である推定相続人である場合において、その「贈与者」が贈与年1月1日において「60歳以上」の者であるときには、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税制度の適用を受けることができる(相続税法21条の9第1項)。親の年齢にかかわらず相続時精算課税制度の適用を選択することができるのではない。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、あくまでも住宅取得等「資金」の贈与を受けた場合に適用を受けることができるのであり、「住宅用家屋」そのものの贈与を受けた場合には、この特例の適用を受けることができない(租税特別措置法70条の2第1項)。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、贈与者の年齢にかかわりなく適用を受けることができる(租税特別措置法70条の2第1項参照)。
不動産鑑定評価基準
(1)
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(最有効使用)を前提として把握される価格を標準として形成されるが、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいているものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が十分な効用を発揮していない場合がある。
答え:○
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが(最有効使用の原則)、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいているものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである(不動産鑑定評価基準第4章Ⅳ)。
正常価格、限定価格、特定価格は市場性を有する不動産について求める価格であるが、特殊価格は、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について求める価格である。
(3)
限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
答え:×
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう(不動産鑑定評価基準第5章第3節Ⅰー2)。本問の記述は、特定価格の定義である。
(4)
文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、正常価格、限定価格、特定価格を求めることはない。
答え:○
正常価格、限定価格、特定価格は、市場性を有する不動産について、市場価値や経済価値を表示する価格であるから、市場性を有しない不動産について、正常価格、限定価格、特定価格を求めることはない(不動産鑑定評価基準第5章第3節Ⅰー1、2、3)。
原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法であるが、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることが「できる」ときはこの手法を適用することが「できる」
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効であり、この手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものには基本的にすべて適用すべきものであり、「自用」の不動産といえども賃貸を想定することにより「適用される」ものである。
不動産鑑定評価基準
(3)
土地鑑定委員会は、公示区域内の土地の鑑定評価を行い、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する。
答え:×
土地鑑定委員会は、標準地について、毎年1回、「2人以上の不動産鑑定士」の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する(地価公示法2条1項)。土地鑑定委員会が鑑定評価を行うのではない。
(4)
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、実際の取引価格を規準としなければならない。
答え:×
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示された標準地の価格(公示価格)を規準としなければならない(地価公示法8条)。実際の取引価格を規準としなければならないのではない。
土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、基準日である1月1日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する(地価公示法2条1項、同法施行規則2条)。
(6)
地価公示法にいう正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合における一定の取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物その他の定着物がある場合、又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
答え:×
地価公示法にいう正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合における一定の取引において通常成立すると認められる価格をいうが、当該土地に建物その他の定着物がある場合、又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が「存しない」ものとして通常成立すると認められる価格をいう(同法2条2項)。
「関係市町村の長」は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない(地価公示法7条1項、2項)。都道府県知事が閲覧に供するのではない。
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合などにおいて、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならないのであって、必ずしも公示価格と同額としなければならないわけではない(地価公示法9条)。
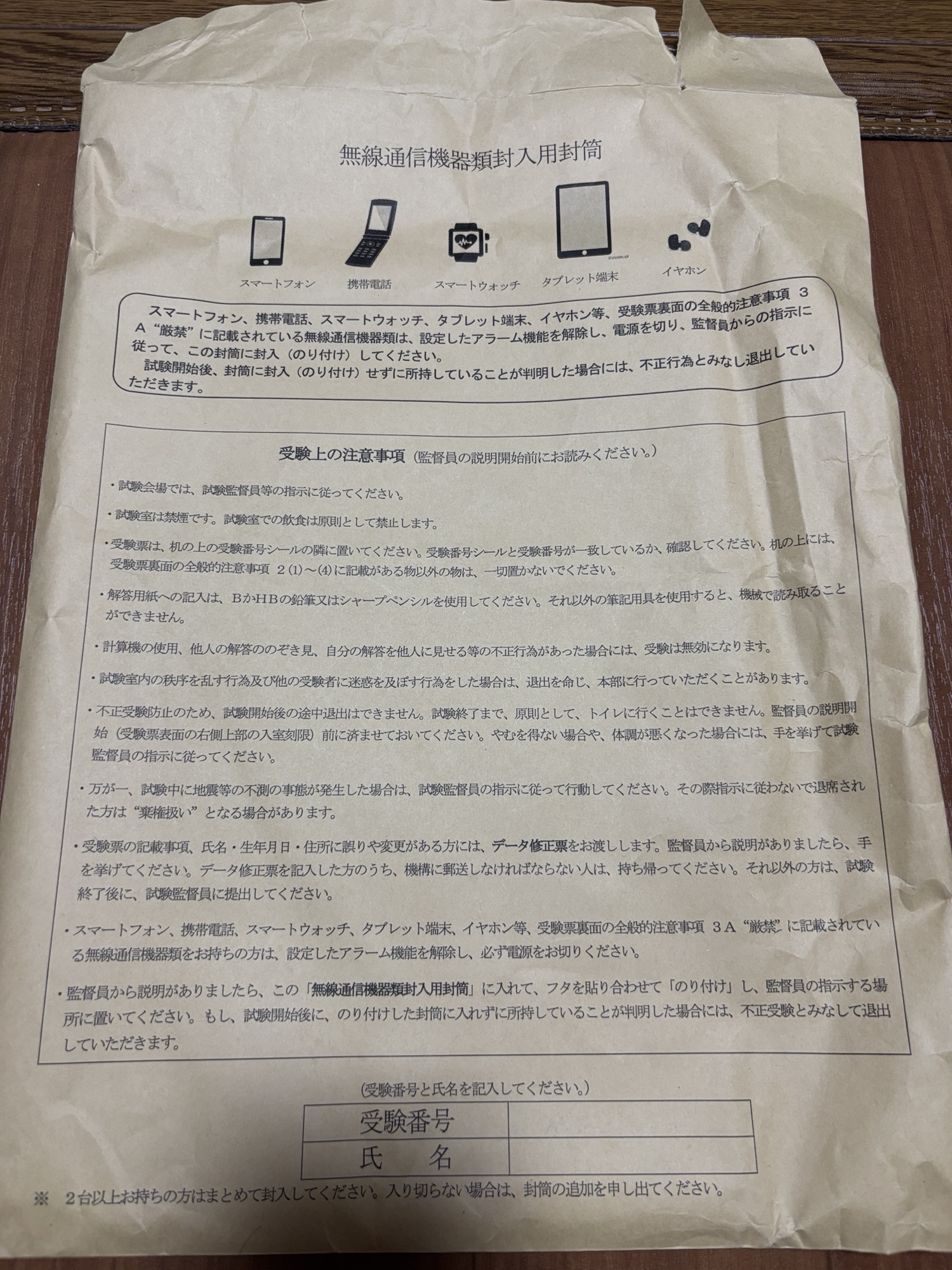
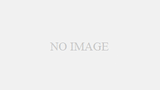
コメント